YOMIKO STORIES
2020.08.13
“マルチバーサル・シフト” に向かう都市と生活者<前編>
ポスト・コロナ時代における社会潮流 「“マルチバーサル・シフト” に向かう都市と生活者」 オリジナルレポートを発行しました。
今回の新型コロナウイルス感染症COVID-19によって、都市の中に見え隠れしていた様々な予兆が世界的な危機に直面することで、一気に表面化しはじめています。
THE FUTURE IS ALREADY THERE IN THE CITY.
YOMIKO都市生活研究所 都市インサイト研究ルームは、都市や地域、場、空間のあり方を通して見た独自の視点で、生活者の未来の兆しを見つめてきました。
“ 新型コロナウイルスを経験した都市と生活者は、これからどこへ向かうのか? ”
私たちがこれまでの研究を通じて着目してきた論点を元に、ポスト・コロナ時代を考えるにあたっての仮説と視点のレポートとなっています。本レポートについて、ルーム長の城雄大とメンバーの山下雅洋、小林亜也子、西村真で、その概要をお伝えします。
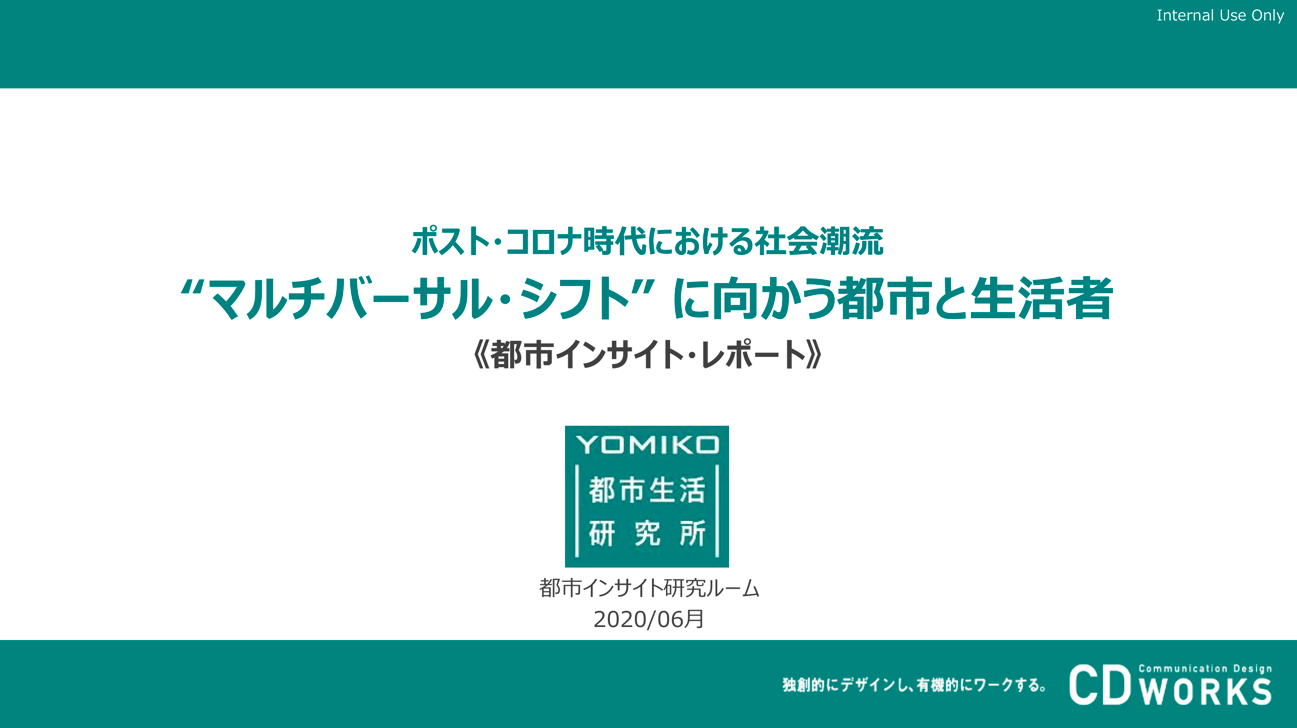
大きな転換期を迎えている世界の都市。私たち都市生活者は、次の時代へ向けた進化を加速させる。それは “ マルチバーサル ” な世界。
城:レポートのタイトルとなっている「マルチバーサル・シフト」。このマルチバーサルという言葉は私は聞き覚えのないものでしたが、その意味をあらためて提案者の山下さんからお願いします。
山下:レポートに出てくる変化や進化の兆しに共通しているものとして、都市も生活者もこれまでとは違う役割や個性を2つ3つ…と複層的に、並行して備えてゆく姿が浮かびあがってきました。ある時はこっちの世界でアクティブに仕事をして、ある時はまた別の顔になって地域活動に勤しむ。まるで2つ3つの時空間を行ったり来たりしながらストーリーが進んでいく、SFやアメリカンコミックの主人公のようです。マルチバーサルという言葉と概念は、元々は理論物理学の言葉でユニバース/ユニバーサル=ひとつの宇宙という概念に対して、いまこの瞬間にも複数の宇宙(時空間)が同時並行的に存在している…という概念の言葉です。
まさにそんなイメージ・概念がぴったりなのでは?と思いました。
城:新型コロナウイルスによって、都市における単一な環境や生活様式に集中・依存することの危険性や脆さが表面化したと思います。ポスト・コロナの不安定で不確実な時代においては、都市も生活者もいかに多様で多面的な存在となることができるか?が、次の成長へ向けた重要テーマになってきているのではないでしょうか。そのようなマルチバーサル・シフトへ向かう都市と生活者の可能性や兆しを、本レポートでは「都市」「地域」「場」「住まい」の4つの視点で構成しています。
都市としての視点:スマート〈レジリエント〉シティ
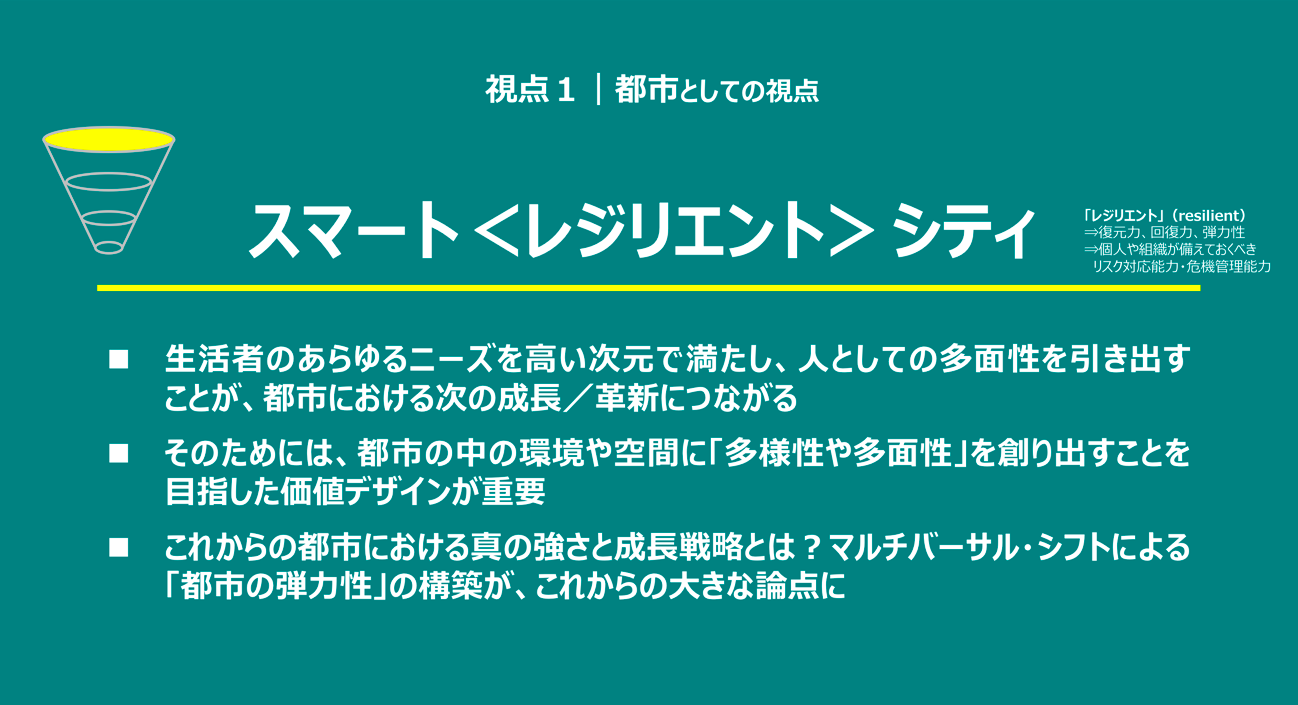
城:コロナ禍の前からこの数年、都市開発の世界では「スマートシティ」への期待が高まっていました。しかし、その議論は行政やインフラ産業としての視点が先行するものであり、生活者のベネフィット視点が置き去りになっている側面があったのではないでしょうか。今回のコロナ禍を経てあらためて都市と生活者の関係性を考え直すことで、スマートシティの議論も大きく進展すると思っています。
西村:Googleの兄弟会社によるトロントでのスマートシティ計画が、奇しくもSTAY HOME期間中に頓挫しました。表向きはコロナ禍による経済停滞〜投資計画の見直しによる撤退となっていますが、昨年からすでに住民の反対運動などで行き詰まりを見せていました。一方でロックフェラー財団は2013年に「危機は21世紀の都市におけるニューノーマルである」と提言し、『100のレジリエント・シティーズ』として世界の都市を対象としたレジリエンス向上への支援を行っていました。これからの都市にとって、この『レジリエンス』というキーワードが非常に重要になってくると思われます。
山下:工業に依存した都市の成長は、とうの昔に限界を迎えていました。これからの時代は都市生活者ひとりひとりの創造性やバイタリティを都市がいかに引き出すか?それによるクリエイティブ産業の育成や文化醸成が、重要な成長戦略になるといわれています。そのためには、どんな災害やウイルスに襲われても簡単には崩壊しない『回復力や復元力』を都市自体が有していることが必要ですが、実はそういう意味でのレジリエンスだけではなくて、さまざまな圧力や変化、さらに多様化・多面化してゆく生活者の価値観やニーズを「しなやかに」受容してゆく都市の『弾力性』という意味でのレジリエンスも、とても重要になってきていると感じます。

小林:たとえば、都市における防犯・防災の機能は長年の課題として整備されてきましたが、これからはそこで暮らす生活者の「免疫力」や「メンタリティ」を高める環境・機能の整備も重要な機能として注目されると思います。産業・経済成長の効率性を追求することで自然や人間として本来必要な環境から切り離されてきた都会での生活に、先進テクノロジーによる後押しも相まってそれらの環境を取り戻す動きが見られます。シアトルのアマゾン新本社のような、オフィスビルの中に緑豊かな自然を内包する巨大空間を創出したり、自然光を再現できるLEDで朝から夕方の1日の太陽光リズムを室内でも再現したり…。それらは人間の本能に働きかけて、免疫力やメンタリティに大きく作用することが科学的にも証明されてきています。
城:たとえば働く場であるオフィスが安らぎの場になったり、憩いの場である公園が仕事をする場になったり、ひとつの都市空間が複数の役割を柔軟に、しなやかに担ってゆくことで生活者の「多様なチカラ」を引き出す…そんなこれからの都市が『弾力性=レジリエンス』の高い都市の姿とも言えるかもしれません。
地域としての視点:ワンマイル型生活圏の再創造
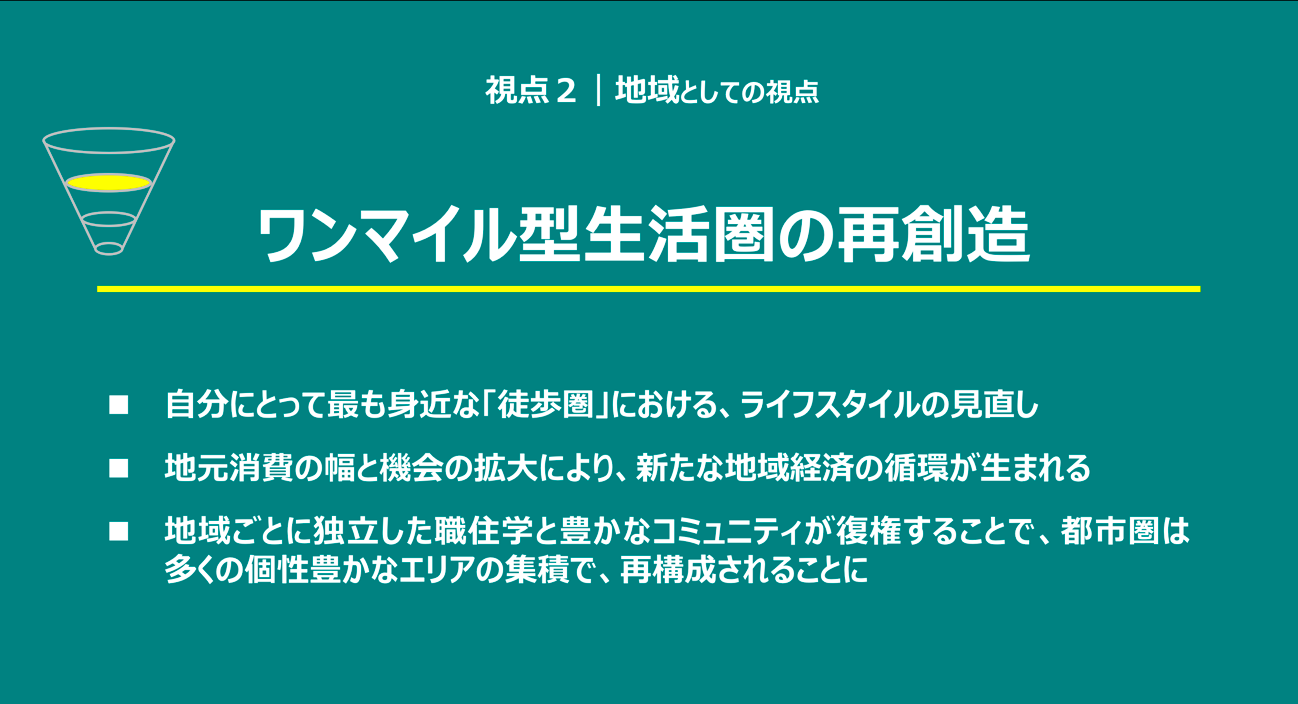
城:つぎは「地域」としての視点です。私たちはSTAY HOMEとして、これまでに経験したことがないような長時間・期間を在宅で過ごしました。これによって地域に対する関与や生活者ニーズが大きく変わりつつあるように思います。
西村:多くの居住エリアは「ベッドタウン」開発の流れをうけて非常に限られた住宅街機能しかなく、豊かなライフスタイルを送るには不足している機能やインフラ、サービスがたくさんあることに生活者は気づきました。建築家の隈研吾さんも「コロナ後は徒歩圏内の都市OSの書き換えが必要」と言っています。過度な一極集中は成り立たず、徒歩や自転車で移動できる圏内で働いたり生活したりすることも求められるようになると。また地元飲食店をテイクアウト購入で応援する「エール飯」という動きも全国に広がり、飲食店をキッカケとして地元への新しいつながり意識が芽生えてゆきました。

城:自分にとって最も身近な「徒歩圏=ワンマイル圏」における、ライフスタイルの見直しが加速すると思います。その流れは地元消費の幅と機会を拡大させることで、地域経済の循環が活性化するのではないでしょうか。地域ごとに独立した職住学と豊かなコミュニティが再創造されることで、個性豊かな小エリアがたくさん育ってゆくことにも期待されます。
小林:地産地消運動の合言葉として、「km0」という言葉がヨーロッパを起点に世界へ広がっていました。もとは農産品や酪農品を中心とした消費の価値観でしたが、それらに限らずポスト・コロナの時代では様々な商材やサービスの地産地消が活性化してゆくはずです。結果として、それらが地域の個性化を促進することで「都市間競争力アップ」にもつながってゆくと思います。
城:地域の個性がより豊かになれば、そこで生活する市民の誇りや愛着=シビックプライドの醸成もさらに活発になってゆくでしょう。地域経済だけではなく、都市と生活者の多様なコミュニケーション・デザインが生まれ、拡がることへも期待が高まります。長年、シビックプライドについて研究〜発信してきた都市生活研究所としては、「日本でも、いよいよ」という感じで嬉しいです。
後日、後編では「場」「住まい」の視点から、マルチバーサルシフトへ向かう都市と生活者のレポートを紹介します。
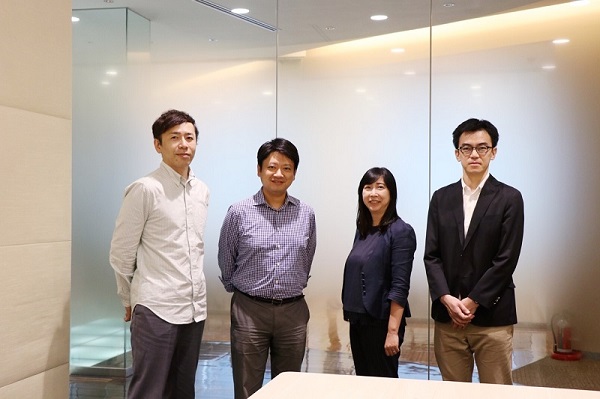
左から、
山下 雅洋/2012年読売広告社入社。都市生活研究所・都市インサイトルーム所属(データドリブンマーケティング局兼務)。インサイトプランナー。ブランディングとインサイトプランニングを武器に、飲料、化粧品・日用品、菓子、自動車など幅広いクライアントのブランディング及びコミュニケーション戦略を担当。インサイトの発掘においては、行動経済学や社会学の知見をもとに、フィールドにおける体感を重視する。モットーは「前提を疑え、体感を信じろ」。
城 雄大/都市生活研究所 所長代理 兼 都市インサイト研究ルーム ルーム長。1999年 読売広告社に入社。マーケティング・プランニングの部門にて、航空会社・玩具/ゲームソフトメーカーなどのクライアントに対するマーケティングおよびブランド戦略に関する業務に従事。2011年より都市生活研究所に所属。主に地域の再開発に関するコンセプト開発/商品企画や都市と生活者のインサイトに関する研究などを手掛ける。大学時代に学んだ民族学での「フィールドワーク視点」を大切に、研究を続ける。
小林 亜也子/2005年読売広告社入社。営業を経て、2008年より都市生活研究所に所属。街づくり、マンション開発、商業、玩具、飲料、食品と幅広い業種・領域で、商品開発・ブランディング・コミュニケーション戦略立案に携わる。特に住領域での商品開発やエリアコンセプト開発を多数担当。近年は、建築家を中心とした有識者ネットワークを活かし、街・場づくりを基軸とした研究(「都市ラボ」「次世代サードプレイスラボ」)に従事。
西村 真/2005年読売広告社入社。営業を経て、2006年より都市生活研究所に所属(2020年8月よりビジネスデザイン局在籍)。不動産クライアントを中心に、住宅、商業、エネルギー企業、自治体までtoC企業、toB企業問わず広く担当。業容は、広告領域ではコンセプト策定からコミュニケーション戦略を中心に、クリエイティブやプロモーションにも積極的に関与。シンポジウムの企画や、自治体では創生戦略やシティブランディングにも関わる。







